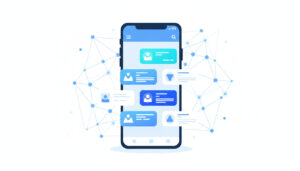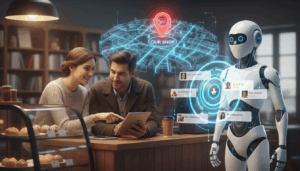Googleが重視するE-E-A-Tの中でも、最も根本にあるのが「T(信頼性)」です。
ユーザーが安心して情報を得られること、そしてサイト運営者が責任を持って情報を管理していること。これらが揃って初めて、専門性・経験・権威性が活きてきます。
この記事では、Web担当者や個人事業主が見落としがちな「SSL更新」「無料SSLと有料SSLの違い」「独自ドメインの信頼性」について、E-E-A-Tの観点から丁寧に解説します。
特に、日々のサイト運用で“気づかないうちに信頼を損ねてしまうポイント”に焦点を当てています。
SSLの更新を怠ると“信頼”は一瞬で消える
SL証明書が期限切れを起こすと、ブラウザは次のような警告を表示します。
「この接続ではプライバシーが保護されません」
ユーザーはこの画面を見た瞬間に離脱します。
ECサイトや問い合わせフォームを持つサイトであれば、即座に売上や問い合わせ数に影響が出ます。
さらに、SSLが切れると
- https → http に戻る
- 混在コンテンツ扱い
- セキュリティエラー
となり、Googleの評価も低下します。
E-E-A-Tの「T(信頼性)」は、
“安全にアクセスできるかどうか”という最低ラインを守れているか
が前提条件です。
SSL更新の放置は、
- 緊急性
- 信頼損失の大きさ
- SEOダメージ
の点で、最も避けるべきリスクです。
無料SSLと有料SSLは何が違い、Tにどう関係するのか
SSL証明書には「無料」と「有料」がありますが、
SEO上の扱いはほぼ同じ です。
どちらも https に対応していれば、Googleは最低限の信頼を認めます。
しかし、E-E-A-Tの“T(Trust)”においては、無料と有料の差が出ます。
無料SSL(DV証明書)
- ドメイン所有者の確認のみ
- 運営者の実在確認なし
- 個人ブログや一般企業サイトなら十分
→ 最低限の安全性は確保できる
有料SSL(OV・EV証明書)
- 企業の実在性を公的に確認
- サイト運営者の責任を第三者機関が証明
- 高額補償が付くケースあり
→ 企業の信頼性を“外部機関が保証”する仕組み
特に以下の業種では、有料SSLが“T”に強く効きます:
- ECサイト
- 医療
- 士業(税理士・弁護士など)
- 建設・リフォーム
- BtoB企業(初見の信頼が重要)
証明書に「企業の実在性」が紐づく点が、最も大きな違いです。
Googleは直接評価しませんが、「ユーザーが安心して取引できる」という観点で、E-E-A-Tの“信頼”は確実に向上します。
独自ドメインは“運営者の責任”を示す最も強いトラスト要素
独自ドメイン(example.comなど)は、E-E-A-TのTを語るうえで欠かせません。
なぜ独自ドメインは強い「T」になるのか?
① 運営主体が明確
無料ブログ(xxx.ameblo.jpなど)は、サイトの主体が曖昧になります。
独自ドメインは
「誰がこのサイトを運営しているか」
を明確にするため、透明性が高まります。
② 運用履歴(ドメインエイジ)が“信頼の蓄積”になる
長期間運用している独自ドメインは
- スパム歴がない
- 一貫したテーマで情報発信している
- 外部からの被リンクが蓄積
といった“実績”を持ちます。
これはGoogleのトラスト評価にも寄与します。
③ メールアドレスの信頼性が上がる
info@example.com
と
example@gmail.com
では、問い合わせの信頼度が大きく違います。
④ 企業・店舗・士業ではほぼ必須
EC、士業、医療、製造業など、信頼が商売に直結する領域では
独自ドメインを持たないこと自体が不安材料になります。
まとめ
E-E-A-Tの「T(信頼性)」は、
- E-E-A-Tの「T(信頼性)」は、
- SSLの正常運用
- 適切な証明書の選択
- 独自ドメインの管理・運用
という、サイトの“基礎”が整ってこそ成立します。
特にSSLの更新忘れは、信頼性を一瞬で失う重大リスクです。
無料SSLでも最低限の信頼性は確保できますが、業種によっては有料SSLで「実在性の証明」を行うことがTの強化につながります。
独自ドメインを長く育て、定期的に更新・改善し、透明性のあるサイト運営を続けることが、何よりの“信頼の証”となります。